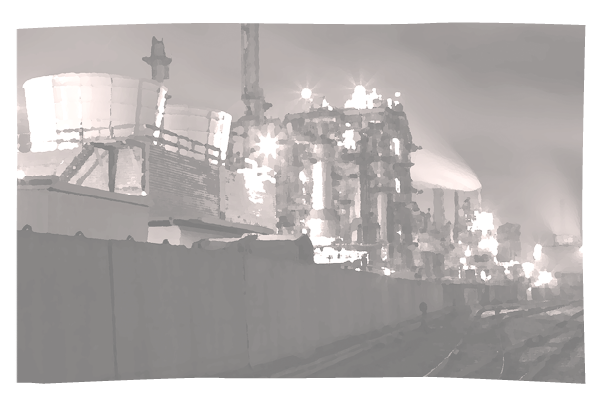
2022.10.14 (09:00)
女房の毒気を含んだ声が達浩の胸を刺した。スドルの父は金鎮求であった。彼は妻より早く帰宅すると、部屋をかたづけたり台所仕事まで手伝ったりした。
「あの家のことがお前と何の関係がある。人は人、お前は自分の家のことだけやればいいんだ」
「私が何をやらなかったのよ。遊んで夕食を作らなかったとでも言うの。私だって…」
「そのくちばしを閉じることができないのか」
達浩は夫の強権をもって黙らせるには黙らせたが、どんより曇った気分を晴らすことは、今もまだできないでいた。
そんなに八つ当たりをしなくてもいいのにと、先ほども建国室の長椅子に寝そべって悔んでいた彼だった。
李達浩は、大切な時間を10分も無駄にした後、鋼鉄を削り始めた。C製鉄所で初めて造った、この工場の鍛造場の労働者が心血をそそいで原型を造りあげた特殊鋼であった。これを100分の1ミリの誤差も出さず、いろいろな長さと、6つの部分に削ってこそ、ピストン・ロットが出来上がるのだ。
その切削工程が非常にむつかしいため、優秀な旋盤技術だけでなく、沈着性と緻密性が要求された。
この付属品がなければ、窒素ガスと水素ガスを圧縮し、液体アンモニアを製造することが出来なかった。現在使われている機械は、日本が敗戦の直前まで使っていた年数物で磨滅がひどく、これではとうてい生産量が保障できなかった。今の状況では、予備の品を自力で解決しなければ、硫安肥料の年間計画量達成は危ぶまれていた。達浩は筆でバイトの先に油を塗りながら、すでに切削した部分と残った部分を目測した。まだやっと、4分の1を削ったくらいであった。鎮求よりはある程度進んでいることで、一応安心はしたけれど、やはり焦りだけは追い払うことができなかった。
「畜生っ、カタツムリの行進のようだよ」
達浩には旋盤の回転がいつもより遅いように感じられた。バイトでもたくさんあれば、回転速度を上げることができるのであるが。
「そうだ!」
達浩は名案がひらめいたかのように、送りの目盛りを2分の1ミリ程度慎重に動かそうとしたが、つい手に力がこもって1ミリ以上を動かしてしまった。
その瞬間、バイトの爪がふわーっと煙を上げ、全部折れてしまった。
(つづく)
短編小説「労働一家」記事一覧
Bagikan Berita Ini














0 Response to "短編小説「労働一家」9/李北鳴 | 朝鮮新報 - 朝鮮新報"
Post a Comment